公開日:2024年05月31日

マンションの中期修繕計画とは、約10年から15年の期間を見据えた修繕計画のことを指します。
共用部分や設備の適切な維持・管理を目的としている点は長期修繕計画と同じですが、修繕のスパンと工事内容の具体性、計画の詳細度などにおいて異なります。
近年ではマンションの改修工事を、長期修繕計画を元にした中期修繕計画へ移行し、工事の規模も「大規模」から「中・小規模」へと変更するケースが増えています。
目次
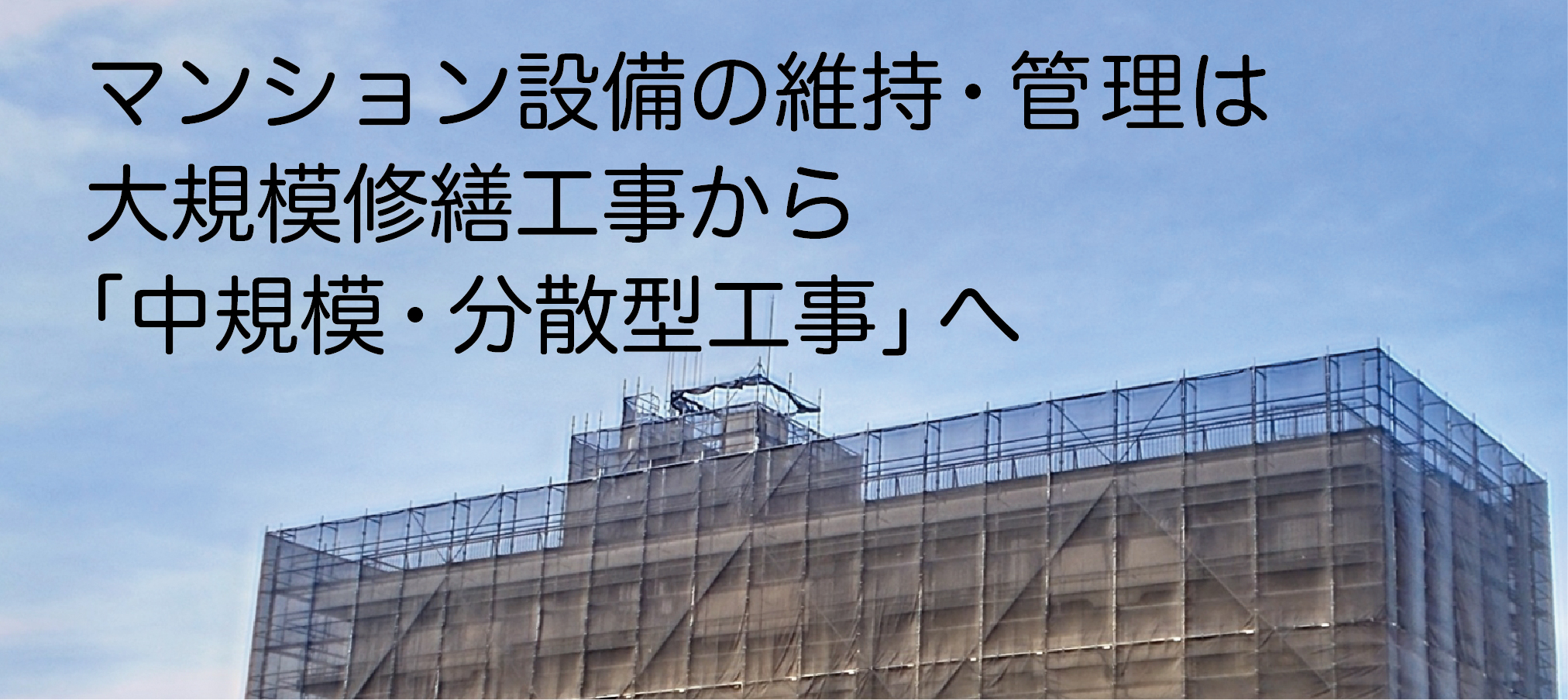
「大規模修繕工事」と「中規模・分散型工事」の違いとは?
従来マンションの修繕工事は、20〜30年のサイクルで考えられた「長期修繕計画」に基づいた「大規模修繕工事」が行われることが主流でした。
 しかし近年では、10年から15年を見据えた「中期修繕計画」に沿った「中規模・分散型工事」と呼ばれる修繕・改修工事が行われることが多くなりました。
しかし近年では、10年から15年を見据えた「中期修繕計画」に沿った「中規模・分散型工事」と呼ばれる修繕・改修工事が行われることが多くなりました。
その大きな違いは、名称の通り「規模」の大小と「期間」の長短ですが、それに伴い「工事内容の目的・具体性」や「計画の詳細度」が変わります。
業者からの見積もりも「◯◯工事一式」ではなく、◯◯日間の工事で材料費や工賃など「具体的な明細」が提示されるため、工事の目的やその費用対効果が明確になると言えます。
「中規模・分散型」への移行が進んでいるのはなぜ?
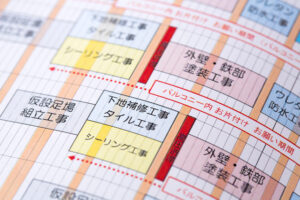 この動きの大きな背景は「工事費高騰」による修繕費の不足があります。経年数の経ったマンションが、一度に大きな工事をするよりも必要最小限の中規模の工事を効率的に進める形を選択するケースが増えてきています。
この動きの大きな背景は「工事費高騰」による修繕費の不足があります。経年数の経ったマンションが、一度に大きな工事をするよりも必要最小限の中規模の工事を効率的に進める形を選択するケースが増えてきています。
 中規模の修繕工事へ移行するメリットのひとつとして、大規模修繕と比べて工事規模が小さいため、工事内容が具体的でその必要性がわかりやすく予算に対する住民の合意形成が取れやすいことでしょう。
中規模の修繕工事へ移行するメリットのひとつとして、大規模修繕と比べて工事規模が小さいため、工事内容が具体的でその必要性がわかりやすく予算に対する住民の合意形成が取れやすいことでしょう。
 また、大規模修繕工事で予定されている「外壁塗装」や「屋上防水」「エレベーターのリニューアル」といった大掛かりな工事より、「水道設備」や「バリアフリー」などのせいかつに直結した工事を優先することができ、住民の現在のニーズに対応ができます。
また、大規模修繕工事で予定されている「外壁塗装」や「屋上防水」「エレベーターのリニューアル」といった大掛かりな工事より、「水道設備」や「バリアフリー」などのせいかつに直結した工事を優先することができ、住民の現在のニーズに対応ができます。

改修工事を「長期」から「中期」に変更するメリットはなに?
実際に修繕工事を「中規模修繕工事計画」に変更し「中規模・分散型」で工事をしているマンションの例に変更したメリットを検証すると、以下のようなポイントがあげられます。
①変更前は、修繕積立金が貯まる前に「大規模修繕工事」を行うため工事資金がショートする傾向にあったが、「中規模・分散型工事」の場合、単年度の会計の中で「できること」を考えて工事を行うため、組合費の累計収支が改善した。
②改修工事を先延ばしにすると優先順位を付けることが難しくなり、結局一度に工事をしなければならないが、中期的なサイクルだと「劣化診断」などを元に優先順位をつけ修繕工事を分散させることができ、工事が効率化できる。
③工事規模が小さくなると、工事の素人である住民も、業者からの「提案」や「見積り」の検証がやりやすくなるので、費用対効果の確認が容易になる。
以上のようなメリットがあるため、「中規模・分散型」工事の流れは、今後ますます広がっていくと思われます。
もっと知りタイム
コスパの良い改修工事をするために


中規模・分散型工事を進めるうえでのひとつのポイントは「工事の範囲を限定」することです。
例えば、「足場」を必要とする工事と不要な工事を別のスケジュールで組むなどの具体的な工夫です。
「足場」はコストも時間もかかる工事なので、足場を養生するのであれば、足場が必要な工事を「まとめて」やる方がコスパが良い工事になります。
逆に言えばそのような大掛かりな工事は少し先延ばしにしてでも、生活環境に直結する「水道設備の更新」や、足場が不要な、屋上、廊下、階段などの工事を大規模修繕工事を待たずに進めていくこともひとつの考え方でしょう。
日常的に情報収集を行い、迅速な判断と住民との合意形成ができる「管理組合」運営をおこなうことが重要です。


 お問い合わせ
お問い合わせ


















 お問い合わせフォーム
お問い合わせフォーム
